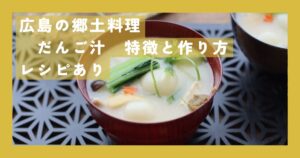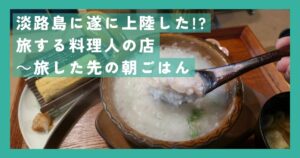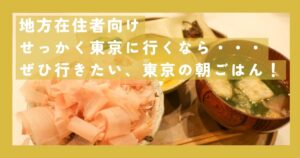みなさん、こんにちは。平山友美です。
福井県小浜市が誇る「若廣」の焼き鯖すし。福井名物として全国に名を轟かす一品です。焼き鯖のジューシーさとシャリが織り成す絶妙なバランスは、他では味わえないもの! 今回は、工場直売所で味わえる作りたての焼き鯖すしを求め、本社へ伺ってきました。焼き鯖すし誕生の背景やその魅力を、今一度深掘りしてみましょう。
- 福井県の焼き鯖すしについて知りたい
- 福井県の名物やお土産を探している
- ヒット商品の裏側を知りたい
という方にピッタリな内容です。
ぜひご覧ください。
焼き鯖すしが全国的ヒットに至るまで
長い歴史があると思われる「若廣」の焼き鯖すしですが、実は生まれたのは、25年前。2000年の福井県坂井市三国町で行われる「三国祭り」への出店がきっかけだったそうです。三国祭りは江戸時代から続く、北陸三大祭りに数えられる歴史ある行事。その際、地元の特色を活かした新しい食品を提供したいと考えた創業メンバーが思いついたのが「焼き鯖を押し寿司にして鯖街道の名物として発信しよう」というアイデアでした。

焼き鯖自体は、福井の郷土料理として親しまれています。しかし、焼き鯖を寿司に使うという発想は、当時は珍しいものだったそうです。「三国祭り」では、200本の焼き鯖すしがあっという間に売り切れたとか。その後も、販売のたびに好評を博し、焼き鯖寿司は地元の名物へと成長していきました。
しかし、その道のりは決して順風満帆ではなかったといいます。しめ鯖を使った寿司が主流だった当時、焼き鯖寿司に対しては「鮮度が低いから焼いているのか」といった疑念もあったそうです。それでも、試行錯誤を重ね、パッケージや販売方法を改善しながら、「若廣」の焼き鯖すしは徐々に支持を集めていきました。最も大きな転機となったのは、国内線の機内食が廃止され、「空弁」として注目されていた羽田空港の販売に参入することができたことだったとか。焼き鯖すしは、一気に全国的な知名度を獲得していきます。
製造過程を目の前にできたてを購入できる直売所

若廣の焼き鯖すしは、国内さまざまな場所で購入することができます。しかし、福井を訪れたなら工場に隣接する直売所へ! 訪問時も、出来立てを買いたいと遠方から多くの人が続々と訪れていました。定番の他にも、季節限定他、特別なバリエーションが並び、異なる味わいを楽しめる点も魅力です。

店内ではガラス越しに工場の様子を見ることができます。スタッフさんが焼き鯖すしを一つ一つ丁寧に手作業で作っている様子を目の当たりにすると、その美味しさの裏側に込められた努力とこだわりがひしひしと伝わってきます。

パッケージを開けてすぐの焼き鯖すしがこちら。棒状のお米に大きな焼き鯖がドン!
若廣の焼き鯖寿司が他の寿司と一線を画す理由は、素材へのこだわりにあります。使用する鯖は、最適な脂の乗り具合と身質を選び抜いたもの。一つ一つ丁寧に骨を取り除き、焼き上げる際には焼き色にも細心の注意を払っているとか。
また、米には福井県産コシヒカリを使用。しっとりとした食感と冷めてもおいしい特徴があります。シャリには甘めのオリジナル酢が使われ、鯖との相性抜群です。ガリや大葉も、焼き鯖すしを構成する大事な要素。大葉は清涼感を与え、生姜は爽やかな辛みで食欲をそそります。これがアクセントとなり、全体のバランスが取れ、味わいをより深めているのです。
常に進化し続ける若廣の焼き鯖すし

現在、焼き鯖すしは、年間80万食以上が売れるという大ヒット商品に。空港、駅、サービスエリア、道の駅、百貨店など、独自の流通網を使い、北海道から鹿児島まで全国で購入できます。しかしやはり、出来たては格別!
常に進化し続け、新しい味わいやバリエーションの開発に取り組み、多くの人々においしい感動を届ける若廣。焼き鯖すしが大人気となった背景には、その美味しさを伝えたいという情熱と、こだわり抜いた素材と製法がありました。できたて、やきたてをガブッとかぶりつくなら、ぜひとも直売所へ!
弊社では新商品の企画開発や販促物の制作、ブランド作りに携わっています。お気軽にお問い合わせください。