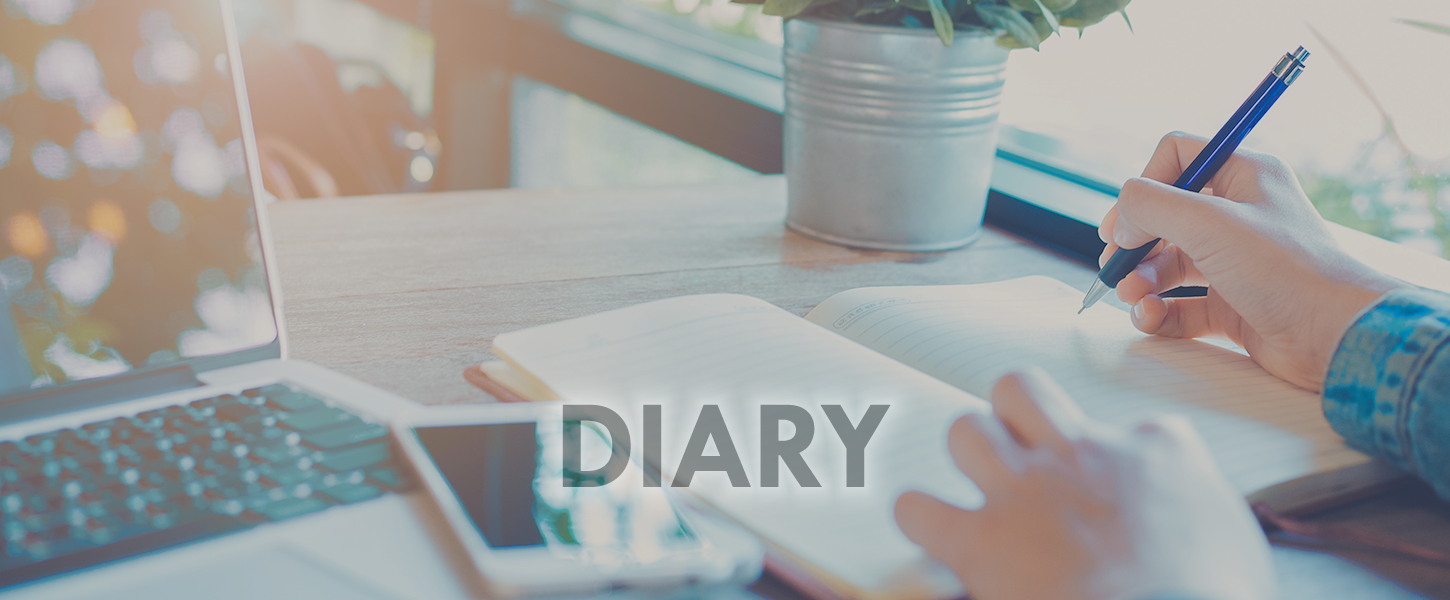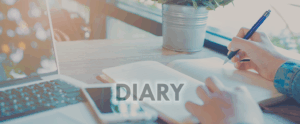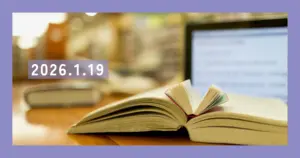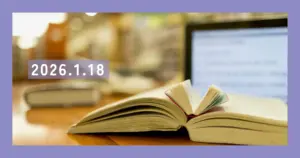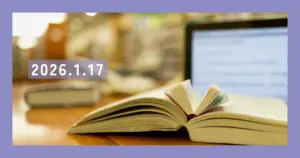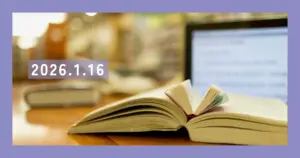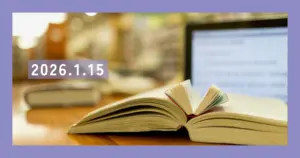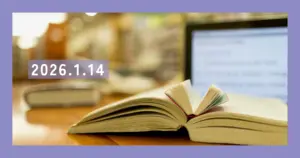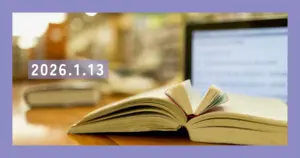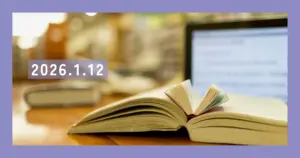前のDiaryで、校了日目前の食の手帖について触れたところ、出版の話になったので、ちょこっと書いてみたいと思います。
私は、地元の出版社(本分社)から商業出版を経験させてもらったのが一冊目。このとき、「本を作る」って楽しいな~と思ったんですよね。著者として書きたいというよりも、むしろ制作することに興味が湧きました。
それから、自分で本を作ってみたい!と言ってみたら、出版社の社長が「やってみたら?」って言ってくれたので、本当にやってみました😊最初から一般書籍は大変そうだったので、小冊子を作りました。ワンコインで買える薄っぺらの本。
だけど、本のサイズやページ数、装丁など色々、自分で決めて、「台割」を決めて・・・ホント、楽しかった!!ちゃんと、流通コードも取って、Amazonで販売しましたし。その後もどんどん、小冊子を出版するようになって、流通したものが6冊、地域内だけの郷土料理本なども含めると10冊を超えます。
これがきっかけで、企業の会社案内やブランドブック、商品カタログなどを作ることができるようになりました。地方だと、デザイナーさんがこれらの制作を手掛けることが多いのですが、デザインという箱からでなく、「コンテンツ」(中身)から作っていくという、今の私のスタイルはこの本を制作したことから始まったのです。
企業の会社案内やブランドブック、商品カタログを中身から作る、って分かる人には分かってもらえると思いますが・・・「事業理解」が鍵です。企業の会社案内やブランドブックを作るのに、社長に会わないわけはありません☆社長インタビューはもちろん、商品理解を深めるために、工場を見せてもらったり、営業責任者にお取引先との話を聞いたり、とにかく会社の広報担当者のごとく、ヒヤリングしていくのです。そして、経営者の考え、会社の理念、目指していること、どうなりたいか、色んな話を聞いたうえで作るブランドブックです。 先日も、数ヶ月おきに1万部も増刷してくれる企業から「お客様からこのブランドブックを見て、信頼できるお店だな、と思って買いに来ました、と言っていただいています」と、嬉しいフィードバックもありました。
このように、私が本の出版によって得たものは、自身の知名度や権威性というよりも、企業からの信頼でした。人からの信頼以上に、企業から信頼を得ることは、難しいものです。企業は組織ですし。うちのような1人でやっている小さな会社・・・というか、ただの個人が法人の帽子被ってるだけ・・・みたいな存在💦 それがこういう制作を通じて、上場企業とのお取引もできるようになりました。
たかが小冊子ですが、されど出版物。ただの自作の絵本じゃなくて、出版社を通しての書籍というものがこんなにも、評価が違うものなのだと気付きました。
しかし小冊子には、欠点がありました。せっかく、流通コード(ISBNコード)を取得してもらったというのに、書店流通が難しいということです。やっぱり、ある程度のページ数はないとね・・・
それから色んな経験をしつつ、多くの制作を手掛けるようになってきたとき、ふと閃いて作ろう!と思ったのが「ひろしま食の手帖」です。今は、2年目の制作ですが、相変わらず楽しいです😌
「ひろしま食の手帖」は、広告非掲載で出版しています。掲載している企業は、こちらの企画に合うところに、コンタクトを取って載ってもらってるだけなので、一切、掲載料はいただいていません。そこで私が「自腹で出してます!」と言うと、ほとんどの方が「自費出版」だと思われるのですが、実は違います。
「自費出版」と「自腹で出版する」は、似ているようで全く違います。
自費出版は、自分でお金を出して出版社に制作をしてもらう、ということです。「自腹で出す」というのは、制作を自社でやっている、という意味です。つまり、本来は出版社がやってくれるはずの制作業務をすべて、私の方でやっているのです。デザイナーさんも、単なるパッケージデザインができる人では難しいのです。出版物を手掛けたことがある人でないと、出版社とのやり取りが難しい😥 出版物を作るにあたり、基本的な知識と経験をもった人を制作チームに入れていないと、素人集団で本はできません。
自費出版だと、出版社にお願いして作ってもらうので、気に入らないデザインを何度も直してもらうことが難しい場合が多いですが、自腹出版(笑)だと、自由度は高いです。そもそも、コンテンツ自体を私が考えて決めているので、デザインがあがってきたときに「イマイチ!」と思ったら、すぐにやり直しをかけることも、大して難しくありません。
企画に合わないものは載せない、 そんなコダワリを貫けるところが最大の強みです。
本づくりに携わってみたい方には、「ひろしま食の手帖」編集部に入ってみて!と言いたい(*^-^*)
と、熱く語った今日のDiaryは終わりです。